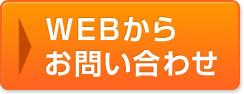足底筋膜炎では、以下のような症状が特徴的です。
①朝の一歩目の激しい痛み
朝起きてベッドから降りた時や、しばらく座っていた後に立ち上がって最初の一歩を踏み出す際に、かかとや足裏にズキっとした強い痛みを感じることが多いです。これは、安静にしている間に足底筋膜が縮まり、歩き始めると急に伸ばされることで強い刺激が加わるためです。
②動き始めると痛みが軽減
歩き始めると徐々に痛みが和らぐ傾向があります。しかし、長時間歩いたり、立ち続けたりすると、再び痛みが強くなることがあります。
③特定の動作での痛み
かかとやその周り、足裏の土踏まずあたりに痛みを感じます。場所は特定できることが多いです。
運動中や運動後に痛みが出たり、運動した翌日に痛みを感じることもあります。
階段の上り下りやつま先立ちの際に痛みが増すことがあります。
足の裏が突っ張るような感覚を覚えることもあります。
④足裏の熱感
炎症が進行すると、足の裏に熱っぽい感じやほてりを感じることがあります。
これらの症状は、足底筋膜への繰り返しの負荷や過度なストレスによって引き起こされます。特にランニングなどのスポーツや長時間の立ち仕事、加齢、足のアーチの崩れ(扁平足やハイアーチ)などが原因となることが多いです。
足底筋膜炎の原因は多岐にわたります。
①繰り返しの負荷
長距離走、サッカー、バレーボール、バスケットボールなど、ランニングやジャンプといった足に強い衝撃を与えるスポーツをしている人は、足底筋膜炎になりやすい傾向があります。硬い地面やアスファルトでの練習も、足への負担を増大させます。また、長時間の立ち仕事も足底筋膜に継続的な負荷をかけ、発症リスクを高めます。
②加齢
年齢を重ねるとともに、足底筋膜自体の柔軟性が低下したり、かかとの脂肪組織が薄くなったりすることで、衝撃吸収能力が低下します。これにより、足底筋膜にかかる負担が増え、発症リスクが高まります。40歳から60歳代に最もなりやすいとされています。
③足の形の異常
足裏のアーチのバランスの崩れも大きな要因です。扁平足(土踏まずがない)やハイアーチ(土踏まずが高すぎる)の場合、足底筋膜に不均等な負担がかかりやすくなります。これらの足の形状は、足底筋膜の機能に影響を与え、炎症を引き起こす可能性があります。
④筋肉の柔軟性低下
ふくらはぎの筋肉やアキレス腱の柔軟性が低下していると、足を踏み出す際に足底筋膜に強い牽引力(引っ張られるストレス)がかかり、炎症を起こしやすくなります。運動不足による足の筋力低下も同様に、足底筋膜への負担を増加させる要因です。
⑤靴の問題
クッション性の低い靴や、足に合わない靴を履いていると、歩行や運動時の衝撃が直接足底筋膜に伝わりやすくなり、炎症の原因となります。
⑥肥満
体重が増えると、体重を支える足底筋膜への負担が大きくなります。肥満は足底筋膜炎のリスクを高める要因の一つです。
足底筋膜炎の治療は、まず保存療法が基本となります。保存療法で改善が見られない場合は再生医療などの外科的治療が必要となる場合もあります。
①薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤の内服や湿布、軟膏などが用いられます。痛みが強い場合は、かかとの部分にステロイド注射を行うこともありますが、これは慎重に検討されます。
②リハビリテーション

ストレッチや筋力トレーニングなどの運動療法、また治療器を用いた理学療法が行われます。
足底筋膜と足首のストレッチ:座った状態で足を膝に乗せ、片手で足の指を反らせ、もう一方の手でかかとを押さえて10秒間キープします。これを片足10回ずつ、1日3セット行うのが目安です。ふくらはぎのストレッチも効果的で、壁に手をついて片足を後ろに引き、アキレス腱を伸ばす方法もあります。
足底の筋力アップトレーニング:足裏のアーチを支える筋肉を鍛えることで、扁平足や外反母趾の予防にもつながります。タオルギャザー(足元に広げたタオルを足指でたぐり寄せる運動)や、ビー玉移しなどが有効です。
③インソールや靴の見直し

足底筋膜への負担を軽減するために、足に合ったインソールや靴に交換することが重要です。
インソール
足のアーチをサポートし、衝撃を吸収するインソールを使用することで、足底筋膜にかかる負荷を軽減できます。特に扁平足の場合、かかとが内側に倒れないようにしたり、土踏まずを高くしたりするインソールが有効です。
靴
クッション性の高い靴を選び、骨格に合った適切なサイズの靴を履くことが大切です。
④再生医療
保存療法で改善が見られない場合や重度の場合は、PRP療法(多血小板血漿療法)などの再生医療が注目されています。これは自身の血液から抽出した濃縮血小板を患部に注入し、自己治癒力を高める治療法です。
痛みを和らげるためのアプローチ
①安静とアイシング/温熱

痛みが強い場合は、過度な運動を控え、足に安静を与えることが重要です。炎症を抑えるために、氷を入れた袋をタオルで包み、患部に10~15分当てる「アイシング」が効果的です。ただし、症状によっては温める方が良い場合もあるため、自己判断せず医療機関に相談しましょう。
②マッサージ
足裏のマッサージも有効です。マッサージボールを使って足裏を転がすと、筋肉の緊張が和らぎ、痛みが軽減されます。ただし過度な刺激は痛みを余計に誘発することがあるため注意が必要です。
③テーピング

伸縮性のあるテープを使ったテーピングで、足底筋膜をサポートし、痛みを軽減する方法もあります。足の状態に合わせて、適切なテーピング方法を選択することが大切です。
予防策
①足への負担を減らす
無理な運動を避ける
足底筋膜に強い衝撃を与えるランニングやジャンプを伴う運動は、炎症を悪化させる可能性があるので、痛む時は避けるようにしましょう。特に運動習慣のない人が急に激しい運動を始めるとリスクが高まります。
長時間の立ち仕事を避ける
長時間足に負担がかかる立ち仕事も、足底筋膜炎の原因となります。適度に休憩を挟んだり、姿勢を変えたりして負担を分散させましょう。
体重管理
体重が増加すると足底筋膜への負荷が大きくなるため、適切な体重を維持することが大切です。
②靴やインソールの工夫
適切な靴を選ぶ
クッション性のある、足にフィットする靴を選びましょう。ヒールの高い靴や底の薄い靴は足への負担が大きくなるため避けるのが賢明です。
インソールの活用
足のアーチをサポートし、衝撃を吸収するインソール(足底板)を使用することで、足底筋膜にかかる負担を軽減できます。扁平足やハイアーチなど、足の形状に問題がある方には特に有効です。
再発防止策
足底筋膜炎は再発しやすいと言われているため、症状が改善した後もセルフケアを継続することが重要です。
①ストレッチと筋力トレーニング
足底筋膜とアキレス腱のストレッチ: 足裏の柔軟性を保つために、足底筋膜とふくらはぎ、アキレス腱のストレッチを毎日行いましょう。特に、朝起きた時や運動後、入浴後に行うと効果的です。例えば、タオルを使って足の指を反らせる「タオルストレッチ」や、壁に手をついてふくらはぎを伸ばすストレッチがおすすめです。
足底の筋力強化: 足裏のアーチを支える筋肉を鍛えることも再発防止につながります。タオルギャザー(足の指でタオルをたぐり寄せる運動)などが有効です。
②温熱・冷却ケア
症状に合わせたケア: 痛みが始まったばかりの急性期にはアイシング(冷却)が、慢性期には温熱が痛みの緩和に役立つことがあります。ただし、自己判断せず、医師に相談して適切な方法を取り入れましょう。
③痛みを我慢しない
痛みを無視して過度な運動を続けたり、足裏を過度にマッサージしたりすると、炎症が悪化する可能性があります。痛みを感じたら無理せず、安静にすることが大切です。
これらの予防策と再発防止策を日常生活に取り入れることで、足底筋膜炎の症状を管理し、快適な毎日を送ることができるでしょう。症状が改善しない場合や悪化する場合は、早めに整形外科や整骨院など専門家のアドバイスを受けましょう。


 072-432-6766
072-432-6766

 メールでのご予約はコチラ
メールでのご予約はコチラ